

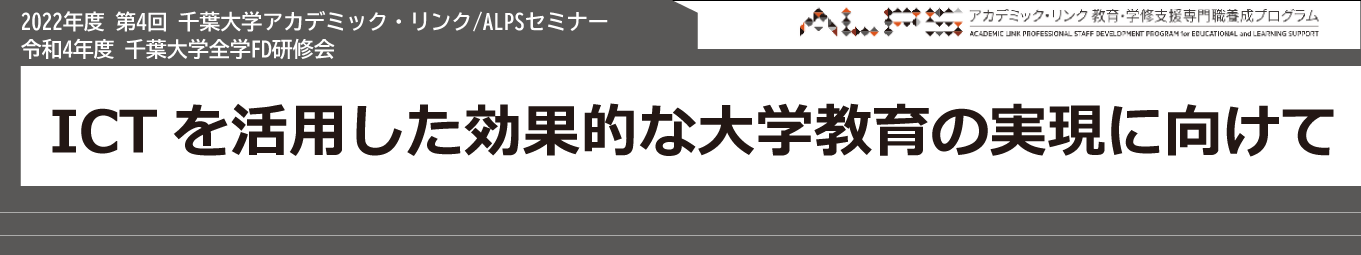
2022年度第4回アカデミック・リンク/ALPSセミナーは、「ICTを活用した効果的な大学教育の実現に向けて」と題し、早稲田大学人間科学学術院教授 大学総合研究センター副所長の森田裕介氏をお招きし、開催いたしました。
セミナーでは、コロナ禍における大学授業の現状と、ポストコロナを見据えた大学授業について講演されました。まず、コロナ以前の大学授業のオンライン化の変遷が説明され、続けてコロナ禍における大学授業の現状が、「効果的オンライン教育のありかたと評価基準・視点に関する調査研究報告書」(https://www.juaa.or.jp/research/document/)をもとに説明されました。報告書からは、オンライン教育そのものに対する否定的な見解は少なく、今後の大学教育のあり方を規定する重要な要素として、多くの大学がこれを積極的な姿勢で評価していること、一方でその推進にあたっては、学内リソースの不足や教員にかかる負担の大きさなど、ハード面、ソフト面で課題があること、そのようななかでも、これまでの授業運営とは異なる構想と展望を持って、各大学で準備を進めようとしている状況が窺えると述べられました。
次に、ポストコロナの大学授業の展開について、早稲田大学の取組みを例に説明されました。ハイブリッド授業にはハイフレックス型やブレンド型があり、いずれの方法も教員に配信作業や教材作成の負担がかかるものの、学生が柔軟に学べることは大きな利点だと述べられました。また、教材作成については、最初から完璧なコンテンツを作ろうとせず、段階的に修正していくことが提案されました。ポストコロナの大学授業については、私立大学連盟の提言(https://xn--shidairen-zf4h027zkvwc.or.jp/topics_details/id=3330)等をふまえて説明され、早稲田大学では、授業アンケートでの学生からの意見も参考にしつつ、授業のデザインやコンテンツ作成の支援、環境の整備を進めていることが紹介されました。
これからの大学授業を考えるうえで、教員には、授業の目的にあったインストラクショナルデザインを選択すること、テクノロジーや教科内容についての知識をアップデートすること、自身が受けた教育の再生産からの脱却を意識すること等が求められてきます。そうした中で、大学全体としては、ますます多様となる授業デザインに対応する環境の整備や、授業づくりにおける教員のサポートをおこない、ICTを活用しながら学生の多様な学びを支えていく必要があると述べられ、セミナーは締めくくられました。
セミナーのアンケート結果はこちらからご覧になれます。アンケート