Symposium / Seminar / Openlecture
シンポジウム / セミナー/公開講座
【ALPSプログラム シンポジウム
著作物の利用環境整備は進んだか:授業目的公衆送信補償金制度開始から3年を経て教育現場から見える課題】
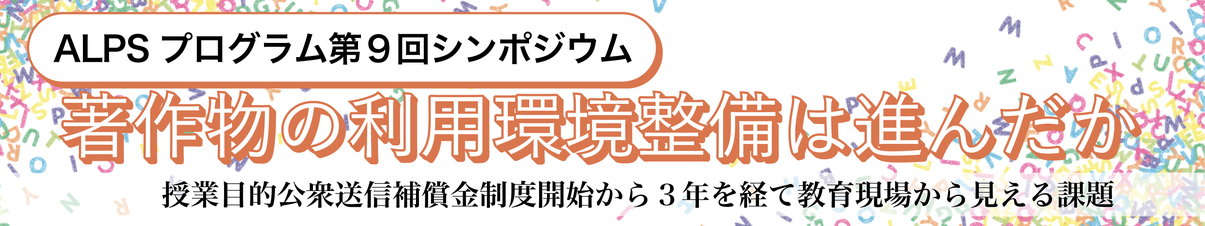
開催日時・場所
- 2023年11月30日(木)14:00-16:30
- Zoomによるウェビナー形式での開催
講師
- 大和 淳 氏(福岡教育大学教育学部 教授)
- 久保田 裕 氏(山口大学知的財産センター 特命教授、(一社)コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事)
概要
2018年の著作権法改正により第35条の権利制限規定の適用範囲が見直され、「授業目的公衆送信補償金制度」が創設されました。その名が示すとおり、授業に伴う「公衆送信」をその形態を問わず著作権者の許諾を得ることなくできるようにするとともに、同時遠隔授業のための公衆送信以外の公衆送信については教育機関の設置者が補償金を支払うこととするものです。この制度は COVID-19パンデミック下の2020年4月に緊急施行され、2020年度は特例的に補償金を無償として運用されました。2021年度からは、児童、生徒あるいは学生の人数を積算基準として決められた年間定額の補償金を支払う方法により、多くの教育機関が本制度を活用しています。
COVID-19パンデミック下では、多くの教育機関でキャンパスや校舎への入構制限がなされ、教育機関は全面的なメディア授業への移行を余儀なくされました。この制度がなければ、例えばオンデマンド型のメディア授業を行う際、引用等の著作権法に定められた権利制限に該当しない形で著作物を利用するには、一つ一つの著作物について著作権者から利用許諾を得なければならなかったはずです。そのような手間をかけることなく著作物を利用できるようになったのは、教育機関にとって歓迎すべきことでした。しかしその一方、「補償金を払っていれば、その教育機関では著作物を自由に利用できる」という誤解が生じていたり、「権利制限が適用される(許諾を得ずに利用できる)範囲はどこまでか」ということを意識するあまり、逆に利用が萎縮しているという話を聞くこともあります。また対面授業に戻ることで、この制度を使わなくなる教育機関も今後は増えてくるかもしれません。
2018年の著作権法改正の趣旨は、教育のICT化、ひいては教育の質の向上のために著作物の利用を円滑に行えるようにすることにありました。この趣旨を真に生かそうとするなら、授業目的公衆送信補償金制度のみならず、当初から議論に上がっていた、この制度を補完するライセンス制度や著作権についての普及啓発など、取り組むべき課題はまだ残っています。
本シンポジウムでは、補償金制度開始後の状況を踏まえて、教育機関の視点から、著作物の利用環境整備の方向性について改めて考える機会としたいと思います。
残念ながらご来場いただけなかった皆様にも、当日の模様を動画配信によりご覧頂くことができます。ぜひご視聴ください(ご利用のブラウザによっては、プラグインのダウンロードが必要です)。
共催
このシンポジウムは、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の共通目的基金の助成を受けて実施されています。
当日配布資料
著作物の利用環境整備は進んだか-これから目指したい姿についての一提案-/大和 淳 氏(福岡教育大学教育学部 教授)
著作権制度の理解が「創作」を促す!/久保田 裕 氏(山口大学知的財産センター 特命教授・(一社)コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事)
シンポジウム動画【前編・講演パート】
シンポジウム動画【後編・パネルディスカッションパート】
ブックレット
ALPSプログラムでは、ALPSシンポジウムの内容を、ALPSブックレットとして刊行しています。
vol.9 著作物の利用環境整備は進んだか-授業目的公衆送信補償金制度開始から3年を経て教育現場から見える課題-(2024年3月)
